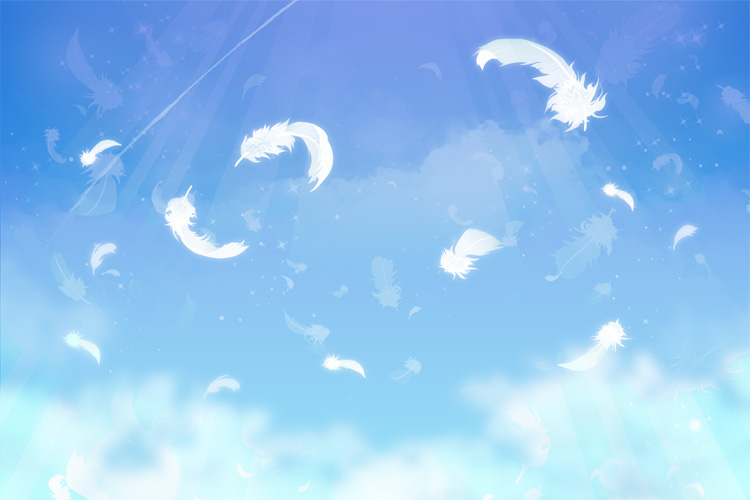茶であり咳であり棘であるもの(後)各地
年ごとに募ってゆく 老いの衰えというものは中々に厄介・・というか虚しいものでもあります。足腰は弱り耳も目も遠くなってくる。持久力は下がり血圧だの消化だの体の基本的な部分にまであれこれ不具合が生じてくる。若い頃はこんなこと
湧水の如き女の性 命をも焦がす物語(前)
『 天城越え 』は歌手 石川さゆりさんによる大ヒット曲、愛の情念に焦がれる女性の心模様が鮮やかに歌い上げられて、演歌にあまり興味が無くてもこの歌は好き!という方も少なくないのではないでしょうか。 「天城越え」は別名「天城
北の大地に織りなす風と岬の伝承 – 北海道
北海道 果てなき地平と北方独特の大自然に抱かれ、国内はもとより海外からの観光客も日本屈指の集客力を誇る景観と豊穣の楽園・・。 地理的に対局の地 南端 沖縄とともに独自の風土と歴史を織りなしてきた北の大地ですが、この北海道
龍の目が開きノギの王子も目覚める – 秋田・岩手県
秋田県の東部と岩手県の西部、つまり両県の県境を跨いで「八幡平」という山地が広がります。間違いやすいですが “はちまんだいら” ではなく「はちまんたい」と読みます。 住所的には秋田県仙北市や鹿角市、
相模国の縁辺から「猫の踊り場」- 神奈川県
神奈川県の領域は その昔 “相模国(さがみのくに)” と言いました。ご存知のとおり「相模湾」などに、今もその名が残っていますね。 但し、現在の県庁所在地・横浜市区域と、同じく大都市である川崎市区域
夢は現実 現実は夢 夢物語から学ぶもの(後)- 大分県
「夢」という言葉を使うとき二つの意味がありますね。 一つは普段 就寝中に見る夢、もう一つは将来的に望む状態や成果に想いを馳せている心情を表します。 どちらにせよ共通しているのは確定的なものはでなく、現実のも
夢は現実 現実は夢 夢物語から学ぶもの(前)- 大分県
空をフワフワと飛んでみたりする夢があるそうですが、残念ながら私はこれまで見たことがありません。 高いところは苦手なので見れなくても構わないのですが、夢の中では得てして非現実的なことでも殆ど疑うことなく受け入
不器用な猪武者を称え小諸の桜 – 長野県
まだまだ寒い日が続きますが皆様には如何お過ごしでしょうか。例年に比べ今年は暖冬なのだそうですが、それでも寒い日は寒い・・。 寒さだけが因でないにしても、昨年末、数年ぶりにひいた風邪にはかなりまいりました。(熱が高く咳が長
月の引力が見える町のアイロニー – 佐賀県
九州北西部、長崎、佐賀、福岡、そして熊本各県で囲まれた海域が「有明海」です。 約1,700km²の面積をもつ九州最大の湾ですが、一般的に有明海と聞いてイメージするのは その北部に広がる比較的浅い水域で、ムツゴロウなどで知
やはり金は金から?八畳敷話の元と妙 – 熊本県
本日 先ずはこちらの歌をお聴きください。「Shall We Gather At The River」日本名「まもなくかなたの(彼方の)」という賛美歌です。 アメリカ・バプテスト教会において1800年代に作られた聖歌の